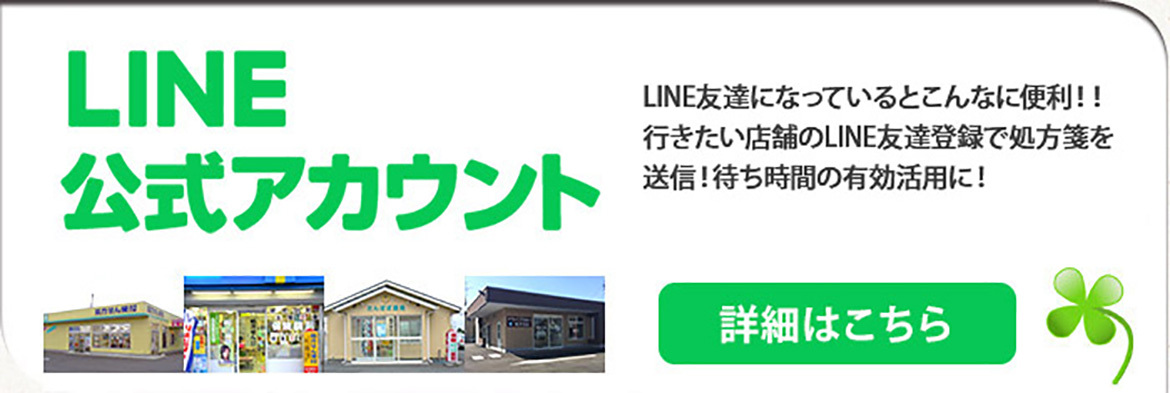介護用品・健康食品幅広い品揃えであなたの健康を守ります
当薬局は、地域密着型のトータルヘルスケアができる薬局を目指しています。
疾病に対する薬物提供のみならず、
予防や健康の維持・増進といった幅広いステージにて地域貢献を行っていきます。
お知らせ
店舗のご案内
施設基準等
医療DX推進体制整備加算
- オンライン資格確認等システムを通じて患者さんの診療情報 薬剤情報等を取得し、調剤服薬指導等を行う際に当該情報を閲覧し 活用しています。
- 当薬局は、マイナ保険証利用を促進する等医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいます。
- 当薬局は、電子処方箋や来年開始予定の電子カルテ情報共有サービス活用など医療DXに係る取組を実施しています。
医療情報取得加算
- マイナンバーカードの保険証利用に対応しています。
- 資格確認を行う体制を有しており、当該保険医療機関を受診した患者さんに対し、受診歴、薬剤情報、特定健診情報、その他必要な診療情報を取得活用して調剤を行っています。
- 患者さんの希望により服用薬剤の種類や服用経過などを記録した「薬剤服用歴の記録」を作成し、薬剤によるアレルギーや副作用の有無を確認するとともに、複数の病院診療所から薬剤が処方されているような場合には、服用薬剤同士の重複や相互作用の有無をチェックします。
- 必要な場合に服薬期間中のフォローも対応します。
調剤報酬点数表に基づき地方厚生 (支) 局長に届け出た事項に関する事項
調剤点数表に基づき以下の算定項目の施設基準を満たし、届出しております。
- 調剤基本料 1
- 地域支援体制加算1
- 連携強化加算
- 後発医薬品調剤体制加算3
- 在宅薬学総合体制加算1
- 医療DX推進体制整備加
明細書の発行状況に関する事項
- 明細書を無料で発行しています。必要のない場合は、申し出てください。
長期収載品の調剤
- 患者さんが長期収載品の処方等又は調剤を希望する場合は、特別の料金として、長期収載品と後発医薬品最高価格帯との差額の1/4を徴収します。
居宅療養管理指導
- みなし介護事業者として事業所の運営規程の概要等の重要事項等は以下の通りです。